今回のテーマは『ジャズの演奏には理論が必要?音楽レッスンを受けてきて思う事』です。
レッスンでは楽器の持ち方から始まり、奏法や理論を勉強してきました。
その中で自分なりに理論を学ぶ事について感じた点をお話させて頂ければと思いますので、参考にして頂ければ嬉しいです。
ジャズのイメージは?
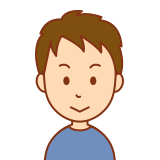
ジャズなんて難しいから弾けない。
私がジャズ演奏を楽しんでいる事を音楽仲間に話すと、結構な確率で言われる言葉です。
たまたま私の周りがそういう環境なのかは分かりませんが、同じような体験をされた方はおりませんでしょうか?
ジャズが難しいと思われるのは音楽理論と結びづけられる事が多いからだと思います。
小学校や中学校の音楽の時間で習った「変ニ長調」や「属七の和音」とか…皆さんも習ってきましたよね。
私は用語だけは響きが特徴的だからか覚えていたりしましたが、結局何のことだったか分からず。
また人によっては「音楽」というカテゴリーには国語や算数とは違う取っつきにくさがあり、これが難解だというイメージに繋がってしまっているのだと思います。
ジャズだけは特殊なジャンル
確かに私もハードロックにのめり込んでいた高校生の頃、音楽理論に対するアレルギーから積極的に学ぼうという姿勢は無し!
勿論ロックの曲をコピーするという事においても、楽譜を見ながら演奏していくわけですから多少の理論的な知識は必要になってきます。
しかしそんなに突っ込んだ理論の習得は不要で、基本的な弾き方やTAB譜の読み方を少し覚えれば、好きなハードロックやメタル等のジャンルが弾く事が出来ていましたし、その演奏技術があればポップスやパンクといった異なるジャンルもカバー出来ていました。
これらのジャンルを横断的に弾く事に大きな抵抗を感じた事はありませんが、やはりジャズだけは「挑戦してみよう」とか「弾けるんじゃないか?」という気にはなれなかったです…。
やはり「即興による演奏=理論が必要」という部分を、大きな壁として感じたんですね。
音楽理論にも色々ある
しかし理論と言っても、簡単に一括りには出来ないようです。
ジャズとクラシックの両方を学んだ先生に聞いたことがあるのですが、同じ音楽理論でも解釈が異なったりする事があるようで、同じ要領で学ぶ事は出来ないそうです。
例えば和声について、ジャズで習って認識していた概念がクラシックでは通用しなかったとか…。
そういう事実からも、それぞれ目的に合った理論を学ばないとダメなんですね。
ジャズであれば「アドリブが弾けるようになる理論」のように。
う~ん、奥が深いです…。更に理論に対するアレルギー反応が強まりそうですね。
理論を知る事で、選択肢が増える
レッスンでも頻繁に理論の重要性を説かれました。
音のインターバルだとか、「ルート、長2度、短3度…」と様々なスケールの構成をとにかく暗記。暗記。暗記。
ジャズには必須だと言われるのですが、一生懸命覚えてもなかなか演奏と直結して考える事が出来ないので、つまらないんですよね(^-^;非常に苦痛でした。
しかし真面目に暗記をして、レッスン中に出されるテストを少しずつクリアしていく事で演奏面との繋がりが見え始めてきます。
「このコードが出てきたら、このスケールが使えるのか!」と言った感じですね。
分かったからと言ってすぐに流暢なソロが弾けるわけではありませんが、音の選択肢が見えてくるだけでも大きな進歩です。
共通言語で話が出来る
そしてこの音楽理論は、セッションの場でも生きてきます。
当たり前ですが、レッスンで先生とだけの会話だけで使用されるものではなく、言ってしまえば世界共通の考え方でもあります。
こんな会話がプレイヤー同士で出来るようになりますし、ワークショップ等でも講師の方に理論を用いて説明した方が、的確に答えを貰う事が出来ます。
このようにコミュニケーションを助けてくれる共通言語としても音楽理論は非常に役立つものとなりますし、知っていれば自分で本や膨大なインターネットからも情報を得て知識とする事が可能です。
このような事からも「音楽理論が分からなければジャズは絶対無理」とは言いませんが、確実に上達の近道にはなると思います。
最近は非常に噛み砕いて分かりやすく解説してくれているYouTube動画などもありますので、それらを参考に少しでも良いので理論に対する苦手意識を変えてみては如何でしょうか?
まとめ
今回は『ジャズの演奏には理論が必要?音楽レッスンを受けてきて思う事』というテーマでお送りしてきました。
・ジャンルによって理論へのアプローチも様々。闇雲に学ぶのではなく、必要な理論を必要なだけ。

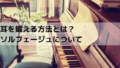
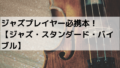
コメント